Report
ドイツだより
vol.1: ニュルンベルクのトイフェアーを訪れて
 ニュルンベルクのトイフェアーは、今年で61回目を迎えました。かつて戦前のドイツでは、玩具取引の中心はライプツィヒ(旧東独)の見本市だったということですが、東西分断後の西側で、メーカーや販売者等、おもちゃ産業にたずさわる人々の需要、要望が高まり、1949年、ごく小規模の展示会として、このフェアーが誕生したそうです。開催地としてこの街が選ばれたのは、木製玩具の他、錫やブリキのおもちゃ、人形、ぬいぐるみなどの作り手が、この周辺地域に多かったという便宜上の理由から。
ニュルンベルクのトイフェアーは、今年で61回目を迎えました。かつて戦前のドイツでは、玩具取引の中心はライプツィヒ(旧東独)の見本市だったということですが、東西分断後の西側で、メーカーや販売者等、おもちゃ産業にたずさわる人々の需要、要望が高まり、1949年、ごく小規模の展示会として、このフェアーが誕生したそうです。開催地としてこの街が選ばれたのは、木製玩具の他、錫やブリキのおもちゃ、人形、ぬいぐるみなどの作り手が、この周辺地域に多かったという便宜上の理由から。
また当地では中世以来、手工芸による物品生産がさかんで、その優れた品質がニュルンベルクの名をヨーロッパ各地に知らしめていたという史実があります。そして、こんな背景こそが、多くの玩具生産者を生む土壌を作ったのだとも言われています。 今や、玩具の国際見本市として世界最大規模を誇るニュルンベルクのトイフェアー。会場の総面積は16万平米に及びます。例えばクリスマスのオーナメントなど美術工芸品的な特色の濃い製品から、マルティメディアを使ったゲーム類に至るまで、展示品の内容も多岐を極めることは言うまでもありません。

さて、このニュルンベルクへは、国際空港のあるフランクフルトから東南方向に列車で約2時間半。まずグリム兄弟の生誕地として知られる隣町のハーナウを通過し、医学者シーボルトゆかりのヴュルツブルクを過ぎる頃、行程のほぼ半分をこなしたことになります。『今夜はいよいよ、日本からやってきたジョルダンのチームと宿泊先で合流』というその日、私は列車に揺られながらある不思議な感覚を楽しんでいました。進行方向に向かって座り、体は確かに列車の速度を感じて、前に運ばれていると意識しているのに、それとは比べ物にならないほどのスピードで、胸のあたりから何かがどんどん後ろに遡っていくような気がするのです。
一年ぶりにジョルダンチームと再会するという懐かしさと、明日からの仕事先に嫌というほど(?)おもちゃが溢れているという意識に刺激され私の記憶がひとりでに過去へと帰って行ったのでしょうか。自分の通った幼稚園の藤棚や、うんてい、鉄棒、砂場、そしていじめっ子の顔までもが、思いがけず目の前に浮かんできます。そんな折、私の中で翌日からのフェアに寄せるある期待が生じました。
それは、作り手の中で生き続けている《子ども》に出会うことです。果たして私の期待に応えてくれた方が二名。今日はそのお二人のことを読者の皆さまにお話します。
レシオ社のロンツィさん
 彼のブースには誰もが戸惑った。「あれなぁに?」「確かによくできてるけど、まさか製品化?」「じゃ、なぜ展示してるの?」
彼のブースには誰もが戸惑った。「あれなぁに?」「確かによくできてるけど、まさか製品化?」「じゃ、なぜ展示してるの?」
…こんな話題を呼んだのは、木製のいわばオブジェ。複雑なジェットコースターでも模したように、曲線、直線が交差している。
はっきり言って意味不明。テープで接着された部分もむき出しで、オブジェとして見るならば、決して美しいものではない。
実は、見るべきものはこの物体そのものではなく、それがブースの間仕切りに映す影の方だった。物体を挟んで間仕切りの反対側に、映画の撮影現場にでもありそうな大きなシリンダー型のライトが一つ。しかもそれがレーン上をスライドしながらオブジェを照らし、その影を間仕切りのバナーに投影するという仕掛けだ。
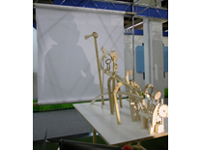
バナーに映ったばらばらのラインや不規則な形が、ライトの移動に伴って動き、ライトがある位置に達した瞬間に、これらすべての断片が収束して一つの具象になる。子どもの横顔と上半身のシルエットが、くっきりと映し出されるのだ。光源はここで静止する。好奇心を隠さず眺めていると、ロンツィさんが話してくれた。製作のきっかけをくれたのは、アート関係のお仕事をしている息子さん。
あるアーティストの、光と影を使った活動にヒントを得て、何かトイショップで役立てそうなものを作ってみては?と、お父さんに提案したそうだ。「これを作るには、数学や物理の課題を解くようなタスクが欠かせなかったように見えますが。」と尋ねると、「計算一切なし。イマジネーションの仕事だよ。作っては投影し、納得行かない箇所に手を加えるという繰り返し。」との答え。「大きく映せば舞台演出に使えそう。」と感想を述べたが、彼は勘弁してくれと言わんばかりに顔の前で手を振って、「そんな大げさな。」と、一笑に付した。

同じライトがブースの別のコーナーにもう一つ。こちらは固定されており、同社の製品《トーテム》その他の積木で作った建物を別のバナーに映している。とてもきれいだ。私達の立ち話の間に、一人の男性がブースに入り、その積木を一つ手に取って吟味すると、それを無造作にテーブルに戻して去って行く。
「ああいうお客さんはね、」とロンツィさんは、さもおかしそうに笑いながら言った。「『ほらご覧、お月様だよ。』と、僕の指し示した指だけを見て、月を見た気でいるんだ。」そして、彼の本意である《月》を次のように語った。
「このコーナーは僕のサジェスチョン。幼稚園でも、家庭でも、灯りを落とすだけで普段と違う空間が生まれる。そこでランプを使って、積木遊びの新しい側面を発見してほしい。作っているそのものだけを見ながら作り続けるのではなく、影の効果を楽しみながらの造形。遊んでいるうちに、積木だけでなく、きっと他の色んなものを映したり、造形の中に取り入れたくなる。帽子、スプーン、自分の髪の毛、他のおもちゃ…、何でもいい。影を見ることで、見慣れたごく日常的なものに、新しい姿を発見できて、すごく楽しいよ。」
私はただただ感嘆し、「《スプーン》なり《帽子》なりの固定観念を離れて、《もの》の新しい姿と意味を知るチャンス。なんだか哲学的ですね。」と、また余計なことを言ってしまった。「とんでもない。」と、彼はさっきと同じ仕草で否定すると、「遊びだよ。」と付け加えた。
そう、数学にも物理にも、舞台演出にも、そして哲学にもはっきりと首を横に振り、ロンツィさんが主張したのは『遊び』だった。そしてさっきのオブジェの方に戻ると、「この仕事のおかげで、もう大人になった息子とも一緒に、ずいぶん遊べた。
そもそも僕自身が、遊び抜きじゃぁダメなんだな。」と、目で笑った。

ディゼーニョ社のヴィヒャルトさん
ラッピングペーパーとお揃いの紙バッグや紙袋。豊富なデザインはどれも可愛いいけれど、お砂糖味がききすぎていなくてほんのりとだけ甘い。こんなディゼーニョ社のデザイナー、ヴィヒァルト夫妻は、私がかれこれ16年余り前、小売店(旧店名:DasSpielzimmer)に就職した当時のオーナー。つまり、私がおもちゃに関わるきっかけとなった犯人、否、恩人だ。もともとおもちゃのデザインとショップ、二つの職業に従事していたご夫婦だが、店を手放して以来、これらパッケージ用品のデザインに専念している。
※当時のDasSpielzimmer正面写真
 ディゼーニョ社社長、息子のダニエルさん(左写真)が、「母のデザインが多い中、今回は父が描いたんだ。」と紹介してくれたのは、ニューアイテム 《City》 。言われてみると、確かに男の子の絵に見えてきた。ビルの谷間を縫う迷路のような道、歩いている人立ち話をしている人、信号待ちや走行中の車には人だけでなく奇妙な生き物も乗っている。見ているだけで知らず知らず喧騒の中に吸い込まれ、思わぬ出会いや発見に驚いたり笑ったりするうちに、たくさんのストーリーも生まれそうだ。「どのくらいかかって仕上げられたんですか?」との同行H氏の質問に「もちろんこういう仕事は、毎日朝から晩までかかりっきりというものではないけれど…」と首を傾げてから、「そうですね、構想から下絵、構図が決まっていよいよ色づけと思いきや、この段階でまた描き直し…、かれこれ数ヶ月、父はこの絵に取り組んでいました。描きながら、時々自分でも笑っていたようです。」とダニエルさん。このとき彼の見せた笑顔は、父子の立場が一瞬逆転したような優しさを湛えていた。
ディゼーニョ社社長、息子のダニエルさん(左写真)が、「母のデザインが多い中、今回は父が描いたんだ。」と紹介してくれたのは、ニューアイテム 《City》 。言われてみると、確かに男の子の絵に見えてきた。ビルの谷間を縫う迷路のような道、歩いている人立ち話をしている人、信号待ちや走行中の車には人だけでなく奇妙な生き物も乗っている。見ているだけで知らず知らず喧騒の中に吸い込まれ、思わぬ出会いや発見に驚いたり笑ったりするうちに、たくさんのストーリーも生まれそうだ。「どのくらいかかって仕上げられたんですか?」との同行H氏の質問に「もちろんこういう仕事は、毎日朝から晩までかかりっきりというものではないけれど…」と首を傾げてから、「そうですね、構想から下絵、構図が決まっていよいよ色づけと思いきや、この段階でまた描き直し…、かれこれ数ヶ月、父はこの絵に取り組んでいました。描きながら、時々自分でも笑っていたようです。」とダニエルさん。このとき彼の見せた笑顔は、父子の立場が一瞬逆転したような優しさを湛えていた。
ご本人不在なのに、ヴィヒャルト氏の胸の中の《少年》に出会えた瞬間だ。しかも、垣間見えたのは明らかに、いたずらっ子の顔だった。
 もちろんおもちゃ業界は、作る側が童心をもってさえいれば、いい製品が生み出せるというものではありません。それでも私が彼らの中の《子ども》に会いたかったのは、数年前に聞いた、ある人気テノール歌手のインタビューが心に強く焼きついているからでしょう。
もちろんおもちゃ業界は、作る側が童心をもってさえいれば、いい製品が生み出せるというものではありません。それでも私が彼らの中の《子ども》に会いたかったのは、数年前に聞いた、ある人気テノール歌手のインタビューが心に強く焼きついているからでしょう。
彼は、同じく人気ソプラノ歌手との稽古合わせをこうコメントしました。
「彼女との稽古は、子どもが二人、遊びに夢中になっているようなもの。お互いに真剣そのもので、しかも、おもしろくておもしろくてたまらないんだ。」
この言葉を聞いて以来、『遊びに夢中になっている子ども並み』の真剣さで収穫された製品や作品に駄作があろうはずがないと私は信じています。主催者の公式発表(ニュルンベルクトイフェアー・プレスインフォ)によると、今年のフェア出展は2625社。約百万点の製品が紹介された中で、新商品が7万点。果たして、各社が競って指差すかなたに、ジョルダンチームはどんなお月様を見つけてきたのでしょう?それはホームページ上のアナウンス、そして6月発行予定のニューカタログにご期待ください。
vol.1『ニュルンベルクのトイフェアーを訪れて』終わり